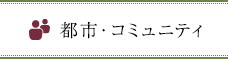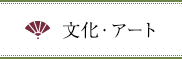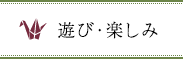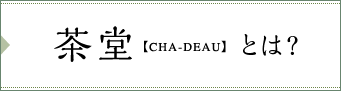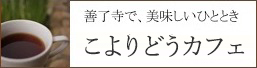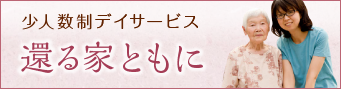- 季節・暦
- 2021年8月29日
君の名は…ヒガンバナ?曼殊沙華?
ここ横浜では、毎年秋のお彼岸の頃に色鮮やかなヒガンバナが花を咲かせます。
暑さ寒さも彼岸まで
ヒガンバナは、朝晩が涼しくなり1日の最低気温が18~20℃になると咲き始めます。最近は気候が変わってきているようにも感じますが、昔から言われているように、お彼岸あたりで暑さのピークが節目を迎えているのでしょう。
ヒガンバナは北海道から沖縄へ、桜前線とは逆に北から南へと花の咲く場所が移っていくのですが、その名称がいくつもあることをご存じでしょうか。
名は体を表す
ヒガンバナの別名のひとつ曼珠沙華(まんじゅしゃげ)。これはサンスクリット語で「美しい赤い花」を表すのだそうです。同様に、花の色や形からアカバナ、ハナビバナ、オミコシバナ、カミナリサンバナと呼ぶ地域があります。
ヒガンバナは花が終わってから葉が生えます。そこからついた名前が、ハッカケクサ、ハヌケイバラ、ハミズハナミズ。
また、地域によって旧暦のお盆からお彼岸にかけて咲く花ということで、オボンバナ、ホトケサンバナ、ボンボンバナと呼ばれることもあります。
そして、お墓の周りなどに咲くことにちなんだのが、ソーシキバナ、シビトグサ、ハカバナ、ユーレイバナ。
球根にアルカロイド系の毒があることからついた名前が、シビレバナ、カブレグキ、ジゴクバナ、ドクユリ。
一方で、腫れ物の張り薬や化膿止め、咳止めの薬としても使われていたことから、クスリグサ、ムクミトリ、ワスレクサ。
球根のデンプンから餅や団子をつくることから、オイモチ、シロイモチ、チカラコ、ケナシイモと呼ばれることもあります。
実はここに挙げたのはほんの一例で、全国津々浦々でおよそ600もの呼び名がヒガンバナにはあるのです。
いのちを守る花
なぜひとつの花にこんなにたくさんの呼び名があるのでしょうか。端的に言えば、ヒガンバナが私たちの生活と密接に関わっていたということです。
大規模な飢饉が起きた時には、大切な栄養源にもなっていたようです。ヒガンバナは、わざわざ栽培しなくても日陰や畔で育ち、球根で勝手に増えていきます。また、毒があるため他の動物にやられることもありません。毒抜きの手間がかかるため、むやみに食用することがなかったので、非常時の救荒食品として重宝されたということです。
今では季節を告げる花としてもっぱら観賞するばかりですが、ただ美しいと眺めていた花にこんなにも多様な名前と用途があったとは驚きですね。
「ヒガンバナのひみつ」かこさとし 小峰書店 1999