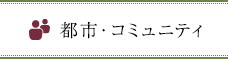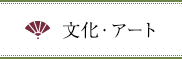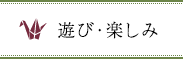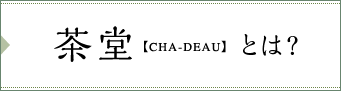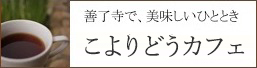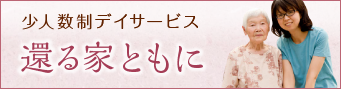こんにちは。
私は2019年4月から瀬戸内海の離島、小豆島で暮らしています。夫と子ども2人と横浜から移住してきました。ここでは島暮らしの日々をお届けします。
今回は、小豆島出身の作家・壺井栄の代表作、「二十四の瞳」についてのお話です。
壺井栄「二十四の瞳」
私はつい最近まで、二十四の瞳を読んだことがありませんでした。
学生時代、教科書のどこかに「壺井栄、二十四の瞳」というキーワードが出てきて、その舞台が小豆島であることまではなんとなく知っていました。でもどんな話かと聞かれたら、「若い女の先生と、12人の子供たちが過ごした話で、反戦がテーマ、だったかな・・・?」という程度の知識で、ちゃんと読んだことはありませんでした。
私たちが小豆島移住してからもうすぐ丸3年になります。
この3年、小豆島のあちこちに、この「先生と子供たち」をモチーフにした看板や銅像があり、なんとなくそれらを目にしながら島暮らしの日々を過ごしていました。
小豆島の玄関口、土庄港のそばの公園にも、先生と子供たちをモチーフにした「平和の群像」というブロンズ像があります。

このブロンズ像の近くに、物語のあらすじが書かれていました。
昭和3年頃、瀬戸内のある寒村の分教場に若い女性教師の大石先生が赴任してきた。
わかい「おなご先生」は当時珍しく、自転車で通勤し、周囲の目をひく。
教え子たちに深い愛情を注ぎ、教え子たちも大石先生を慕うようになる。
小学校卒業後の教え子のそれぞれの人生、結婚後の大石先生の生活が描かれるなか、
日本は満州事変、太平洋戦争へと突入していく。
戦争の犠牲になり、戦死したかつての教え子。
時は過ぎ、終戦後の同窓会では先生や残った教え子たちが与えられた逆境の中で
母として女性として力強く新しい時代を生きていくであろうことが暗示されている。
(小豆島土庄港の平和の群像の碑より)
ちゃんと読んでみようと思ったきっかけは、先日、6才の娘が図書館でこの作品の漫画版を借りてきたことでした。
漫画なので話の展開がわかりやすく、娘に解説しながら一緒に読みました。娘も全部は理解できないものの、ところどころのエピソードには興味を示していました。
「大石先生って本当にいるの?」
一緒に漫画版を読んだ娘の感想は、「大石先生って本当にいるの?」というものでした。
「これは作った話だよ」といってもどうにも納得がいかない様子。
それもそのはず、
大石先生が赴任した岬の分教場の舞台になった田浦(たのうら)分校は、今もそのまま保存されており、その近くにある映画のセットを保存した「二十四の瞳映画村」にも一度いったことがありました。
大石先生の生家の近くにあるという「一本松」の松の木も、今もその場所にたっていて、本を読んだあとに一緒にいってみました。

物語の舞台となった田浦にある「二十四の瞳映画村」には映画の撮影のために作られたセットがあり、木造の校舎の外には古い自転車が止まっています。

そこで私も「あっこれ、大石先生の自転車だね!」と言ったので、娘はますますわけがわからない様子。漫画版にも、大石先生がさっそうと自転車にのって現れ、岬の人々が「若い女の先生が自転車に乗ってくるなんて!」とびっくりしたシーンがとても印象的に描かれていました。
「だからさ、大石先生は本当にいたんでしょ?」となるのも無理はありません。
「作り話だけど舞台は小豆島で、岬の分教場のモデルは本当にあって、それがここの田浦分校だよ。大石先生の通勤ルートというのは一本松から田浦までの、いつもよく通る道のことだよね。先生が足を怪我したときにのった渡し舟は、今でものれるよ。大石先生と子供たちが再会する本校っていうのが、あなたが通う小学校がモデルで、原作にはないけど映画に出てくる電車ごっこをするシーンが、よくピクニックをする池田の城山なんだって。ほら、いま観光シーズンだから、期間限定のボンネットバスも走ってるね~」
と詳しく説明すればするほど、これはますます事実とフィクションの区別は難しいだろうなあと思いました。

(渡し舟乗り場)

(映画村内の、先生と子供たち)

(分教場)
「大石先生は本当にいた」としたほうが、よっぽどわかりやすい。
それくらい、作中に出てくる土地の位置関係やモデルになった小学校、村の雰囲気、海や山や空気、人々の言葉まで、いまの暮らしにも馴染んでいるものばかりです。
小豆島は瀬戸内海では淡路島に次ぐ大きさがあり、人が住んでいる集落もたくさんありますが、たまたま、この物語に出てくる「岬」「一本松」「本校」などの場所が私たちの小さな生活圏にぴったりおさまっていることも、物語にリアルさを増す要因になっています。
また、映画村や舟、ボンネットバスも観光の一環として整備されていて昔ながらの雰囲気をふんだんに醸し出しているので、「ここで教えていた」「ここで子供たちと再会した」「あのシーンはここのこと」とリアルに体感できる楽しさがあります。
ほんとうにいまでも、先生が自転車で通勤し、浜辺で歌を歌い、怪我をした先生を心配してこどもたちが遠い道のりを歩いてお見舞いにでかけるシーンがそこかしこに展開しているような気がしてきます。

作品のファンが舞台となった場所をめぐる「聖地巡礼」の面白さってこういうことなのかな、と、この作品の舞台を巡りつつ思いました。
いちねんせいの瞳
その後、原作も初めてちゃんと読んでみました。
私の最初の感想は、「えっ、先生が子供たちと岬の分教場で過ごしたのってたった1学期だけなんだ!」でした。
岬の分教場で先生を取り囲む子供たちのイメージがあまりにもよく使われ印象的だったので、そのシチュエーションが物語の大部分を占めていると思っていましたが、
2学期初日に先生が足を怪我して渡し舟で搬送されてからは、アキレス健断裂のために岬まで通えなくなり、子供たちに別れを告げて、道の途中にある本校の小学校に異動になるという展開でした。
1年生だった子供たちが成長して5年生になってからの本校での再会や、先生が結婚・出産・終戦を経て再び岬の分教場に赴任するという流れで物語は続いていきますが、「若いおなご先生といちねんせい」が岬で過ごした日々は、思っていたよりも圧倒的に短い時間でした。
それでも、「いちねんせいになったら、毎日小学校にいくんだ。先生と友達とお勉強したり歌をうたったりして過ごすんだ!」という新しい生活へのわくわくした気持ちはいまも昔も変わりなくあり、その部分が物語にも鮮烈な印象を残しています。
岬の分教場のいちねんせいの始業の日の様子は、こんなふうに初々しく描かれていました。
今日はじめて親の手をはなれ、ひとりで学校へきた気負いと一種の不安をみせて、一年生のかたまりだけは、独特の気負いを見せている。三、四年の組がさっさと教室へはいっていったあと、大石先生はしばらく両手をたたきながら、それにあわせて足ぶみをさせ、うしろむきのまま教室へみちびいた。(中略)
今日はじめて教壇に立った大石先生の心に、今日はじめて集団生活につながった十二人の一年生の瞳は、それぞれの個性にかがやいてことさら印象ぶかくうつったのである。
一年生の独特の気負いと一種の不安。入学の日をまつばかりの、小豆島で6才を迎えた娘にもそっくり重なる姿です。
令和4年の春休み。岬の分教場のそばのベンチで、娘は二十四の瞳のまんがを読みながら
入学の日を楽しみに待っています。

小豆島も少子化で、奇しくも娘の学校の新一年生も12人ほど。
戦争とはまた違った「禍」のさなかではありますが、
今年の「二十四の瞳」と先生の出会いは、どんな物語を紡ぐのでしょうか。
参考文献
21世紀版少年少女日本文学館11 二十四の瞳 壺井栄 講談社
書き手・イラスト :
喰代彩 (ほおじろあや)
横浜市出身、善了寺のデイサービス「還る家ともに」で介護士として働いていました。現在は小豆島にIターン移住して三年目、二児を育てながら島の暮らしと、善了寺デイサービスの思い出について書いています。(「瀬戸内 島暮らし」、「ばあちゃんたちのいるところ」として連載中)