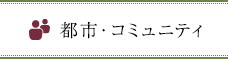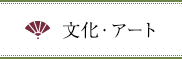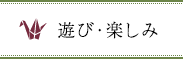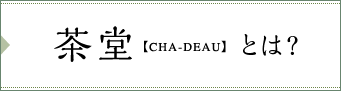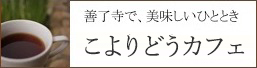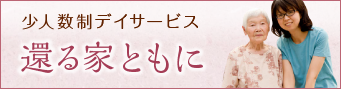- 人・暮らし
- 2015年7月29日
江戸時代の時刻は季節で変わる?絶対時間を使わないスローな暮らし
江戸時代の時刻は季節で変わる?絶対時間を使わないスローな暮らし
現代とはさまざまな点で異なっていた江戸時代の暮らし。時刻の数え方もそんな違いのひとつです。江戸時代には「九つ、八つ、七つ……」のように数字で時刻を表す方式(延喜式)と、「丑三つ時」などのように十二支を使って表す方式(十二辰刻)の2つがありました。今回はこのうち、延喜式の時刻の数え方から江戸時代の生活を垣間みてみましょう。
「時そば」は、どうしてお代をごまかせたのか?
江戸時代の時刻の数え方を題材にした有名な落語に「時そば」があります。深夜の夜鷹そばを舞台にした滑稽話で、お代を支払う際に時刻を聞くことで、1文の代金をごまかすというもの。この話をより楽しむためには、江戸時代の時刻の数え方を知る必要があります。
江戸時代の時刻の数え方とは
延喜式では、日の出から日の入りまで、日の入りから日の出までをそれぞれ6等分し、そのひとつを「一刻」として時刻を表します。「正午」と「深夜」をそれぞれ「九つ」として、そこから「八つ、七つ、六つ、五つ、四つ」と一刻ずつ減っていくという数え方でした。このうち、夜が明けはじめるころを「明け六つ」、日が沈んで空が暗くなりはじめるころを「暮れ六つ」と呼びます。ちなみに、昼の「八つ」はお昼どきから日の入りまでの、ほぼ真ん中の時刻を指しており、そこから「おやつ」という言葉が生まれたと言われています。
代金をごまかした質問は「今、何時?」
さて、「時そば」の舞台となったのはちょうど「九つ時」。現代の時刻でいうと深夜12時ごろです。当時のそばの代金は16文と相場が決まっていました。小銭しか持ち合わせていなかった男は、「ひい、ふう、みい、よう、いつ、むう、なな、やあ……」とそばのお代を数えている最中に「今、何時(なんどき)だい?」「へい、九つでい」と会話を挟みます。そのまま九をとばし、すかさず「とう、じゅういち……」と数えることで、1文をごまかしてしまったというお話です。
季節によって、時間の長さは変わる
さて、江戸時代の時刻の数え方について、もう少し踏み込んで考えてみましょう。当時は、時刻の数え方が日の出入りを基準としているため、季節によって一刻の長さが変るのが当たり前でした。
昼の一刻が夜の2陪になる夏至
昼の長さと夜の長さに一番差が出る、夏至を例にとって考えてみましょう。仮に「明け六つ」を午前4時ごろ、「暮れ六つ」を午後8時ごろとすると、昼の長さは16時間、夜の長さは8時間ということになります。つまり、昼の一刻は約2.7時間、夜の一時は約1.3時間と、倍以上も差が出てしまうのです。
日が昇ったら昼、日が暮れたら夜
現代に暮らす私たちにとっては、複雑にも思えるこの時刻制度。季節によって昼夜の時間の長さが変わるだけでなく、1分単位で時刻を表すこともできないため、どうやって時間を管理したのかと不思議に思う人もいるかもしれません。
しかし、それはあくまでも、忙しく時間に追われる現代に生きる私たちの感覚。時計を持っている人などほとんどいなかった江戸時代では、江戸城内やお寺などに設置された鐘の音によって「明け六つ」と「暮れ六つ」を判断していた程度で、「1分」「1秒」といった細かな時間を管理する必要性がそもそもなかったのです。延喜式の時刻の数え方は「日が昇ったら昼、日が暮れたら夜」という単純明快なものであり、このシンプルな感覚が江戸時代の人々には支持されていました。
シンプルでゆるい江戸時代の時間感覚
現代のように絶対時間を使わず、日の出入りによって時刻を決めていた江戸時代。その時間感覚は一分一秒に追われるようなものではなく、シンプルでどこかゆるさを含んだものであったことがうかがえます。現代に暮らす私たちが、同じような感覚を持つことは簡単ではありませんが、時には時計を外して、太陽の動きに身をゆだねて生活してみるのもいいかもしれませんね。
参考: