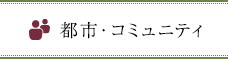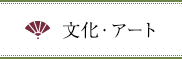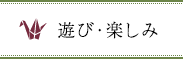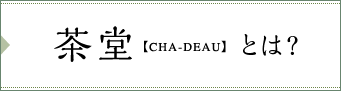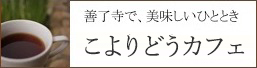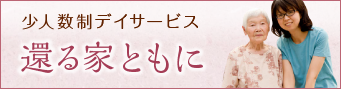- 人・暮らし
- 2016年9月5日
300年以上も続く伝統的な「江戸野菜」。地産地消の食生活を楽しもう!
みなさんは「江戸野菜」という言葉を耳にしたことがありますか? 江戸時代に日本では農業技術が発達し、大根やなす、ねぎ、しょうがなど様々な農産物が生産・流通されるようになりました。そしてその多くが現代も生産され、私たちの食生活を豊かな物にしてくれているのです。今回は、江戸時代から伝わる農業や伝統的な「江戸野菜」を紹介しながら、地産地消の食生活を見つめてみましょう。
将軍に栽培を命じられ、江戸っ子に愛された「練馬大根」
生で食べても煮込んでも、お漬物にしても美味しい大根。日本人の食卓に頻繁に登場する野菜の代表の1つですよね。大根というとパッと頭に浮かぶのは、白くて長いあの形が一般的ですが、実は大根には地方によって様々な種類が生産されていました。
その代表格として今回注目したいのが、五代将軍・徳川綱吉が栽培を命じ、享保年間からこの名前が定着していた「練馬大根」です。当時、人口100万人を超えた江戸の需要にこたえる野菜の供給地として、練馬大根の栽培も発展。その後、明治以降には、たくあん漬けや干し大根が作られ、販売されるようになりました。現在ではその生産高は当時より減っているものの、たくあん漬けは今でも有名な品です。またこの練馬大根は繊維質が多く煮崩れしにくいため、地元ではおでんや煮物にもよく用いられているのだそうです。
お中元の贈答品に使われ、代名詞となった「谷中しょうが」
疲れた体へのスタミナ補給食材として、今でも重宝される「しょうが」。江戸野菜の中には「谷中しょうが」と「八王子しょうが」の2種類がありますが、保水力のある肥沃な土地の谷中で生産されるしょうがは、筋が少ない上にあまり辛くないのがその特長です。谷中しょうがは歯ざわりと風味が良く、味噌をつけて食べると絶品。江戸っ子たちに愛された野菜のひとつだそうです。
また、このしょうがは収穫時がお盆時期のため、商人や職人、谷中の寺社がお中元の贈答品に利用したため、よりいっそう人気が出ました。そのため「谷中」の名は、しょうがの代名詞ともいわれるようになりました。明治以降、市街化が進み、しょうがの生産の大半は埼玉県へ移っていったものの、今でも「谷中しょうが」は東京の市場や居酒屋などでは、定番の一品として人気があります。
かつての魅力を再発見された「内藤とうがらし」
江戸では、バラエティーに富んだなす科の野菜も各地で作られていました。そして、実は「内藤とうがらし」と呼ばれるとうがらしも、このナス科の野菜に含まれているのです。
「内藤とうがらし」は、江戸の宿場町・内藤新宿で作られており、蕎麦に添える薬味として、そのピリピリした辛さが重宝され大流行していました。当時は新宿近辺の畑が真っ赤になるほど生産されていたそうですが、次第に大量生産される「鷹の爪」に押されて、現代ではほとんどお目にかかれないものとなっていました。
しかし、2008年に「内藤とうがらしプロジェクト」が立ち上げられ、戸塚地区(現高田馬場・落合・早稲田)で本格的な栽培が再開。内藤とうがらしを通して、地域の魅力を再発見しようという動きが進んでいます。2015年には「とうがらし女子」の結成や街バルイベントへの参加なども行い、精力的に活動を続けています。
まとめ
このように、現代の東京で暮らす人々の食生活の中には、江戸時代に生産されていた野菜が、現代でも同じように生産され彩りを添えています。かつての人気を失っていた野菜も、「内藤とうがらし」のように復活を果たし、その魅力が地元で引き継がれようとしています。300年以上も続く伝統的な野菜を、現代の私たちが新鮮な状態で食べられるほど贅沢なことはありません。ぜひ自分の地産で生産される地方野菜に目を向け、地産地消の食生活を楽しんでみましょう。
その他の「江戸時代の食」に関する記事はこちら
参考: